肺がん
呼吸器にできる悪性腫瘍について(呼吸器内科・呼吸器外科)
l. 肺がんとは
1.肺癌の発症数と死亡数および今後の予測
日本では平成5年より肺癌の死亡者数は男性においては第1位、女性においては第3位となり、平成15年の死亡者数は、男性で約41000人、女性では約 15000人、悪性新生物全体に占める割合は、男性で22.3%、女性では12.3%、さらにその数は今後も増加の傾向を辿るといわれています。
原因は喫煙率の高さと人口の高齢化といわれていますが、喫煙率は日本も下がった(男性の喫煙率は過去の70%%台から40%台に低下)とはいえ、欧米諸国と比べると、まだまだ若年者や女性の喫煙は低下したとは言い切れず、また喫煙の影響が20年先であることを考え合わせると、今後も増え続けることは想像に難くありません。今から10年後の肺癌死亡数は2005年の倍になると予測されているほどです。
更に、日本は世界一の長寿国ですが、これも肺癌の発症数に大きく影響しています。癌(悪性腫瘍)のうちでも、肺癌は他の癌と比較すると発症する年齢が高齢に傾いており、以前は感染症やその他の癌で亡くなっていた人数も多かった訳ですが、これらを乗り越えると、肺癌が待っているのです。
最近では石綿曝露による、肺癌罹患率の上昇も言われております。横須賀では以前より造船業を中心に石綿曝露歴のある肺癌を多く経験しています。非喫煙で石綿暴露がない人に対して、石綿暴露のない喫煙者は約10倍、非喫煙で石綿暴露のある人は約5倍、喫煙歴と石綿曝露歴の両方がある場合は約50倍の発癌率があると言われています。
2.肺癌(呼吸器悪性腫瘍)とは?
呼吸器悪性腫瘍とは、空気の通り道のうち、気管・左右に分かれてからの気管支・その先の細い気管支や肺胞(酸素交換をする小さな肺の小部屋)にできる、悪性腫瘍の総称です。最も多いのは、細い気管支から肺胞にかけての領域にできるもので、肺野型肺癌(末梢型ともいいます)と呼ばれており、男女ともに増加しています。
肺野型肺癌では喫煙も影響していますが、直接煙が接触する気管支に刺激を与えるのではなく、煙その他"発がん"を誘発する物質の吸入、ないしは摂食等により体内に入り込み、血液中に循環して癌を発症させる化学発癌とされており、受動喫煙もこれに含まれます。X線検査(検診などで行う胸部レントゲン撮影も含まれます)やCT検査(最近では"らせんCT"、"高分解能CT"の機能を併せ持ったものがさらに威力を発揮します)で、発見の機会が増えています。
これに対して、太い気管支の領域に発生するものは肺門型肺癌(中心型ともいいます)で、喫煙の影響が最も大きく、他に六価クロムその他職業性に吸入するガスなどが原因となっています。こちらは肺野型と比較するとその比率は減少しています。太めの気管支の位置に発生するので、気管支刺激による咳や、痰の増加、血痰などで判かることがあり、さらに進行すると太い気管支の根本が閉塞したり、肺炎となることもあります。この場合X線でわかるまでには時間がかかりますが、気管支内視鏡(気管支鏡)や喀痰細胞診でわかる場合もあります。
ll. 肺癌の症状
1. 肺門型
肺門にできる癌では刺激による咳や、痰の増加、血痰などがあり、さらに進行すると太い気管支の根本が閉塞することによる無気肺や閉塞性肺炎となることもあります。
この場合X線でわかるまでには時間がかかりますが、気管支内視鏡(気管支鏡)や喀痰細胞診でわかる場合もあります。
以前から喫煙を続けている方では、喫煙指数*が高い、40歳以上を満たす方ではこれら2つの検査を早めに受けられた方が早くわかる場合があります。
2. 肺野型
一方、肺野型のものでは初期には自覚症状は少ないものです。しかし、進行し癌が大きくなれば肺門型と同様の症状や、癌が胸膜を破って肺の外へ浸潤すると胸水や胸膜転移を来たします。
ここまで進むと手術の効果がないほどに進行していることになりますので、早い時期にX線で発見できるように定期健診を受けられる方は毎年欠かさず受診しましょう。CT、特に"らせんCT"は短時間に検査でき、発見率も向上していますので、喫煙指数の高い方、家族に癌の多い方や、一度癌に罹かられた方には有効な方法です。
*:喫煙指数;一日の喫煙本数x喫煙年数(一日20本で40年なら800)400以上で肺癌が起き易い状況となり、600以上で肺癌の高危険度群とされています。
lll. 診断
1. 肺癌検診
一般に胸部レントゲンと喀痰細胞診による健康診断が行なわれています。その有効性については否定的な意見もありますが、健診で肺癌が早期発見され、手術にて助けられることはよく経験することです。
横須賀市では平成16年度 1万8千人の健診受診に対し、8人の肺癌発見を認めています。喀痰細胞診は、喫煙指数で肺癌発生の高危険度とされる方を対象に、痰を調べ肺門型肺癌の早期発見を目標にした検査です。
近年胸部CTによる健診により、ごく早期の肺癌の発見に有効で、当院でもCT健診をしています。しかし、CT被爆による発癌率の増加が問題となったこともあります。
最近では癌健診にPET(ポジトロン・エミッション・トモグラフィー)健診が注目されていますが、当院では施行できません。できる施設が限られており、まだ普及はされていませんが今後の成果に期待します。
また、採血による健診も行なわれています。腫瘍マーカーの測定ですが、肺癌では、レントゲンなどの画像所見より有効とは言い難いようで、かなり進行していないと異常値を呈さないと考えたほうがいいようです。
2. 肺癌の確定診断まで
確定診断には病理診断が不可欠で、一口に肺癌といっても部位別の分類の他に病理組織学(顕微鏡)的には数種類に分類されます。
●小細胞癌
気管支の太い領域に発生することが多く、喫煙者に多いという特徴があります。日本での頻度は、全肺癌のうち10~15%程度です。抗がん剤や放射線が良く効くので、それらの治療を行います。
●腺癌
ヒトの体の中には汗や粘液を分泌する腺組織がありますが、それらに類似した構造を作って癌組織となるものがあり、日本人に多い胃や大腸がん、乳がんも腺癌です。肺癌で最も多いのがこの腺癌で、さらに細かい組織にも分けられています。女性にも多いのがこの腺癌です。比較的増殖速度は遅く、早い時期に発見され、手術で摘出されてしまえば、治癒が期待できるのもこの癌です。
●扁平上皮癌
小細胞癌と同じく気管支の太い領域に発生することが多く、喫煙者に多いという特徴があります。頻度は、全肺癌のうち20~30%程度です。無気肺や閉塞性肺炎を来たしたりすることも多い癌です。
●大細胞癌
腺癌と同じく、肺の末梢に発生することが多く、頻度は10%以下です。成長速度が速く、急速に進行することがあります。
●その他
低悪性度群と呼ばれる、グループとして太い気管支・気管にできる腺様嚢胞癌、粘表皮癌や肺末梢にもできるカルチノイド等があります。このほか腺癌と扁平上皮癌が30%以上混ざり合った腺扁平上皮癌や2つ以上の種類の癌が混ざり合った混合型があります。さらに珍しい特殊型もあります。
X線、CTなどの画像診断で肺癌が疑われる場合、その腫瘤(しこり)の一部を生検して、顕微鏡診断することが診断確定のための方法です。
組織の一部を採取する生検方法には、気管支鏡で見えるところにあれば、直接腫瘍の一部分を囓り取り、気管支鏡では直接見えない肺野の末梢の方では、X線モニターでガイドしながら腫瘍の一部を採取してくる経気管支鏡下肺生検(TBB)法があります。また、当院では、超音波気管支鏡を用いて、気管・気管支近傍の通常では穿刺が困難な部位の生検も行っています。
この他、皮膚を局所麻酔して、CT(や超音波)で見ながら腫瘤に針を刺し、針の中に残っている組織を顕微鏡で見る、CT(エコー)ガイド針生検法もあります。
上記内科的な方法で診断が付かないが癌が疑わしい場合では、全身麻酔で、胸を開けて(多くの場合胸に2~3ヶ所穴をあけ、胸腔鏡で見ながら、腫瘤の一部か全部を切り取り、急いで顕微鏡で見て、癌か否かを診断し、癌であればそのまま癌の根治手術に移行する、術中迅速病理組織診断法もあります。迅速診断をするには、手術器械等の設備の他、この方法に慣れた病理検査技師と病理医の存在が不可欠です。
肺癌のうちでも肺野も末梢に発生する腺癌などでは、しばしば、この方法(術中胸腔鏡下生検)をとる機会も増えています。
lV. 病期(ステージ)
肺癌の病期決定方法:
肺癌の組織診断が下された後は、治療法の決定をするため、病状の進行を判断する必要があります。これを病期と呼び、I期からIV期まであります。腫瘍自体を示すT因子と、リンパ節の転移を示すN因子と、遠隔転移を示すM因子にわかれます。
* T因子は、CT等の画像で腫瘍の形態と周囲との関係で評価し、0~4に分類されます。簡単には以下のようになります。気管支の太い領域に発生することが多く、喫煙者に多いという特徴があります。日本での頻度は、全肺癌のうち10~15%程度です。抗がん剤や放射線が良く効くので、それらの治療を行います。
T0 = 腫瘍が判明しない。 T1 = 径3cm以内の肺内腫瘍。 T2 = 径3cmを超える肺内腫瘍。
T3 = 肺外の膜まで浸潤している。 T4 = 周囲臓器に浸潤している。
* N因子の検査として、CT・MRIなどの検査に加え、全身麻酔下で縦隔鏡を行い、生検する方法があります。現在では、PETを用いることで、侵襲が少なく検査する方法も検討されています。0~3に分類されます。
N0 = リンパ節転移無し。 N1 = 原発腫瘍の近くのリンパ節まで。 N2 = 同側のリンパ節までの転移。
N3 = 対側リンパ節までの転移。
* M因子は、血液を介して転移を起こす易い、脳・肝臓・副腎・骨の検査を行って判断します。ここでもPETの有効性も言われています。転移のないM0と、転移のあるM1に分類されます。(注:専門的にはもう少し詳細に分類されます)以上のT・N・M因子を踏まえて、病期(Stage)が決められます。
Stege IA : T1 N0 M0
Stege IB : T2 N0 M0
Stage IIA : T1 N1 M0
Stage IIB : T2 N1 M0
T3 N0 M0
Stege IIIA : T1 N2 M0
T2 N2 M0
T3 N1,2 M0
Stage IIIB : T1~4 N3 M0
T4 N0~3 M0
Stage IV : T1~4 N0~3 M1 遠隔転移有り
病期は以下に述べる治療を決めるのに大事な指標となります。肺小細胞癌については、上記の病期に加え、限局型LD(StageI ̄IIIA)と進展方ED(Stage IIIB,IV)に分ける場合もあります。
V. 肺がんの治療方針
まず当院では、肺癌診療ガイドライン(日本肺癌学会/編)にしたがって、肺癌の治療を行っています。
手術療法
1. 外科的治療
病理組織学的診断の、小細胞癌以外を総称して非小細胞肺癌と呼び、これらは一定の条件を満たせば、根治するには手術が適しています。
すなわち、非小細胞肺癌のうち、l~ll期とlllA期の一部は手術治療のみか、または手術の後に抗がん剤(場合により±放射線治療)を併用することで治癒が期待できます。
標準的手術方法: 1.開胸術 + 2.肺切除術 + 3.縱隔リンパ節郭清術
1. 開胸術
癌を含めて肺を切取ってくるには、肋骨(あばら骨)で囲まれた胸腔内(胸の中の空間)に手術器械が入り込んで、切分けする必要があります。従来のやり方では、肋骨を1本切取ってそこから大きく胸をあける方法や、肋骨の1ヶ所を切って胸をあけ手術後に戻す方法などを行っていました。この場合、胸の皮膚を切るのは約15~20cm前後になります。
2. 肺切除術
肺癌を根治的(再発しないように確実)に切取るには、最低でも肺葉の単位で切取る事が必要です。肺葉は、右は3つ(上葉、中葉、下葉)で、左は2つ(上葉と下葉)ですが、2つ以上の肺葉にまたがって癌がある場合には(片方の)肺全摘術となります。しかし肺活量が充分でない患者さんでは、全摘術あるいは肺葉切除でも困難な場合があります。
その場合には、肺部分切除術や肺区域切除を行うこともあります。また、気管支の根元近くに癌がおよんでいる際に、気管支の一部も切除して縫合(継ぎなおす)ことで、他の肺葉も余計に切り取らず、肺の容積を残すようにする気管支形成術も可能です。(図1-a-c)
3. リンパ節郭清
他の癌と同様に癌のできた臓器の部位を大きめに切除する事に加えて、リンパ節を切取る事も必須となります。左右の肺の間を縱隔といいますが、ここのリンパにはしばしば転移が見られます。
図1-a
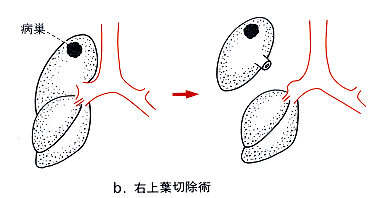
図1-b
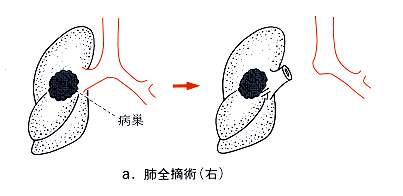
図1-c
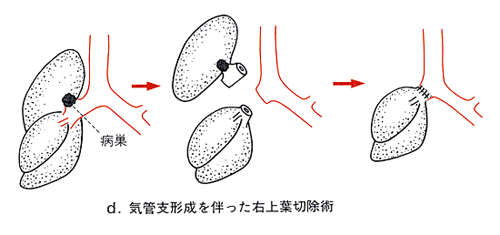
最近の手術法のご紹介
1. 小開胸
従来の開胸法では大きく皮膚を切り、筋肉を切り、肋骨を大きく広げる目的の鋼鉄性の器械(開胸器)を使用しましたが、この傷の痛みは相当大きなものでした。最近、当院では傷を小さめ(5-7cm程度)とし、筋肉もできるだけ切らない、また可能な限り肋骨間の隙間の広い前方側でシリコン製の開創器(金属で肋間を広げない)を使用しています。
2. 肺切除術
癌に対する根治性を維持するには、肺を少なくとも肺葉切除以上で切取るのは同じです。肺葉を切取るには、肺葉に向かう肺動脈、肺静脈、肺葉気管支を縫合(縫って)、切り離す操作が必要ですが、小さい創では、自動縫合器を使用します。肺の末梢にできた小さな癌では、部分切除術や区域切除も可能です。また、肺葉にはまたがっていないが、癌が気管支の太い領域まで広がっていて、一見肺を全部切除する必要がありそうに見える場合でも、気管支の一部を切って縫って(短縮し)、肺全摘を回避する、気管支形成手術+肺葉切除術も当院では可能です。
3. リンパ節郭清
一般的にはリンパ節郭清術も省略はできませんが、肺の末梢にできた小さな癌で、進行していないと判断される場合では、Key Pointをおさえて、そこに転移がなければリンパ節郭清を省略しても治療成績が変わらないという事実が証明されてきています。
これら新しい1.2.3.の方法に胸腔鏡(胸腔をテレビモニターに映し出すカメラ)をを組み合わせると、胸腔鏡(補助)下肺葉切除術といい、当院ではこの方法を80~90%の患者様に応用して取り入れています。
また肺癌といいますと、若い(すなわち40~50歳代)には少なく、そのピークは60歳代後半から70歳代ですが、しばしば80歳代の患者様もいらっしゃいます。
80歳代の患者様の手術が可能であるかは以前より議論となるところですが、これは学会などでもある程度結論が出ていて、決して暦の年齢が全ての判断基準ではなく、その患者様が普段どれだけお元気に、自立して(生活の独立ではありません)生活され、心臓その他の臓器合併症をお持ちでないか、に関わってきます。年齢がお若くてもいくつか他の重症な病気をお持ちであったり、重要な臓器機能の低下のある方では逆に手術が不可能な場合もあります。高齢者では、特に胸腔鏡補助手術となってから、術後経過に及ぼす影響が良好で、最近でも若い年代の方々とほぼ同様の術後経過を辿っています。高齢者の術後成績に関しては、後述のV.もご覧ください。
この他に、手術だけでは充分ではなかったと(手術後に)判明した場合には、補助(追加)治療として、抗がん剤や放射線治療を行うことも可能です。しかし、手術後の体力低下のために、全ての患者様に治療ができるとは限りません。また手術直後に免疫力の低下などで、急激な再発が起こることも時に見られるので、体力の充分な時期に先に抗がん剤治療をしてから、その後に手術を行う導入化学療法(Induction Therapy)もケースバイケースで採用しています。
2. 外科的治療による術後合併症
合併症には、1.手術の前から患者様が持っている病気の悪化等の場合や、2.手術手技の未熟さ、出血時などの判断ミス、手術内容の過剰、不完全などから発生する術中合併症、3.術後不可抗力で起こってしまい回避は困難であったものの、病状の発見の遅れや、追加治療開始決定の判断の遅れなどにより、不可逆的となり生命に直結してしまう状況などがあります。
しかし、1.は術前状態の管理を徹底的に行う事により回避可能である場合も少なからずあり(糖尿病状態や高血圧の管理・コントロール等)、術前管理の問題です。2.は習熟した専門医の存在と、その施設での経験数(年間手術件数)が多いほど、その危険性はより低下します。3.が狭義での術後合併症となり、肺炎・間質性肺炎・不整脈・術後せん妄・術後の声がれ等、一定のリスクで起こりうるものや、全身麻酔時や術後に使用する薬剤の対するアレルギー等必ずしも完全には避けては通れない病態や、心筋梗塞や脳梗塞・脳出血、肺動脈血栓症などの患者様の状態によってリスクの異なる全身の血管系合併症などもあります。しかし、当院では各診療科が充分なスタッフを揃えており、①術前からの全身状態管理、経験豊富(特に開胸手術は横須賀三浦地区では、当院でしか手術に対応していません)な全身麻酔管理が可能であり、③の狭義の術後合併症においても、各疾病の専門医に相談・治療依頼が随時可能で、治療開始のタイミングを逸しなければ、診療器材も充足しており、術後合併症による、術死・術後在院死は年間0-1程度です(手術件数は、1年間で全開胸手術件数が約180件、肺癌・転移性肺腫瘍に対しては約90-100件です。)
3. 外科的治療後(退院後)の外来通院
肺癌に対する術後経過観察は、原則として初期~中期期間までは呼吸器外科外来に於て外来通院で行います。術後初期段階では、手術そのものの経過(傷の痛みや反応性の咳・息切れ感・発熱・反応性胸水貯溜など)の観察目的では1~2回/月程度を2~3ヶ月行い、それ以降は1回/1~2月程度となります。半年~2-3年の間、継続で通院され、再発の様子がなければ間隔をあけていったり、呼吸器内科に移る場合もあります。術後追加治療が必要な場合や、その他の呼吸器疾患が並存する場合には、早期に呼吸器内科にお願いする場合もあります。
術後の外来診療では、手術の後の体調維持・管理だけでなく、再発の有無をチェックする事も重大な責務です。血液検査やレントゲン写真のほか、定期的なCT検査(1~2回/年程度)、PET検査、アイソトープ検査などを行う事もあります。
4. 内科的治療(抗がん剤/放射線治療/支持療法/緩和医療)
小細胞癌の殆ど(ⅠA期の一部では手術をすることもあります)とⅢA期以上の非小細胞肺癌のうち、治療効果が期待できる状態の患者さんで体力等が充分である場合には、抗癌剤治療を行います。
抗癌剤治療は、現在は点滴治療が主体です。 シスプラチン、カルボプラチンのいずれかに、パクリタキセル、イリノテカン、ジェムザール、ドセタキセル、ナベルビンのうち1剤を加える治療法が主体です。病状、体力に応じて適宜治療薬剤・量を変更します。副作用である嘔気・骨髄抑制に対しては有効な治療薬があります。しかし、脱毛に関してはきびしい状況です。
当院では外来治療室を用いた通院による日帰り治療も積極的に行っています。また、間質性肺炎の副作用で使用に注意が必要なイレッサという飲み薬に関しても、適応症例を選んで慎重に使用しよい成績をあげています。
基本的に治療を希望される患者様には、告知が原則で、医師は治療成績、予後などをご本人に説明し、治療を決めていくことにしています。
放射線治療は、当院では現在のところ、通常の放射線治療でコバルトを用いて、頭部・肺局所に治療しています。いずれはリニアックに変更する予定です。
進行の程度が著しい場合や治療を希望されない患者さんには支持療法や、緩和医療を行っています。当院には緩和ケア病棟はありませんが、入院患者さんについては緩和ケアチームがあり、主治医と相談し対応しています。
在宅医療など:
また、在宅医療に関しては、横須賀市内の在宅緩和医療を行っている開業の先生にお願いして病診連携を用いて、在宅の希望をかなえています。
Vl. 肺がんの治療成績
1. 非小細胞肺癌に対する、日本の標準的治療成績 (図2)
非小細胞肺癌においては、Ⅳ-1)でお示しした標準的手術を行なうと、およそ以下の様な術後生存曲線(5年生存率)になると言われています。
横軸が手術日を0日として、以後の経過月数を示します。縦軸が手術の後に生存している方の割合を示します。(n=914名の患者様)
最も進行の程度が浅いStageⅠA(腫瘍が3cm以下で、リンパ節転移なし)で5年生存は84%で、以下進行していくに従い、生存率が低下していくのが判ります。
(図2)
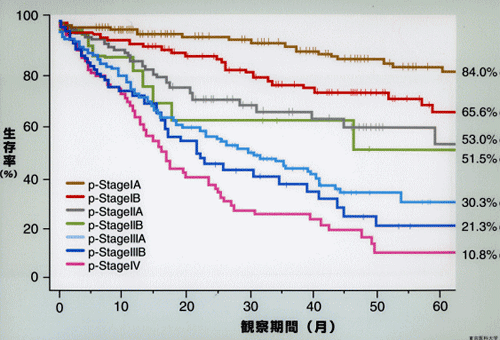
(図3)
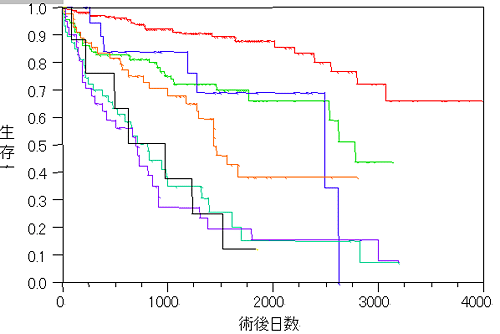
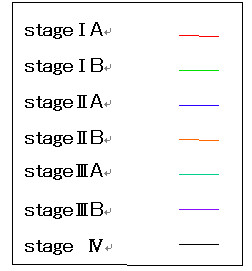
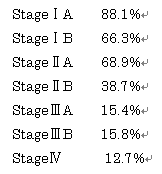
Vll. 当院の呼吸器内科・外科診療の特色
当院は三浦半島地区で、呼吸器内科医・呼吸器外科医・放射線科医が常勤し、総合的な癌治療が可能な病院です。また、セカンド・オピニオンなど患者さんの権利についても、要求に応えるべく努力しています。
また、肺病理を専門とする2名の病理医とともに、毎週カンファランスを開き討論をして、常に患者様の利益となる医療を心がけています。
呼吸器科として連日当直をしていることで、かかりつけの患者様に対し24時間対応が可能となり、不安を抱え在宅されている患者・家族の支えとなっています。

